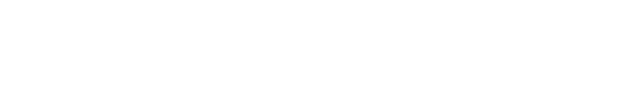当院の特徴
1 最新の医療機器
耳鼻咽喉科用コンビームCTやドロップスクリーンをはじめとした最新の医療機器をそろえております。
コンビームCTでは中耳炎、副鼻腔炎といった感染性疾患において、感染部位や性状など詳細な評価が可能です。
副鼻腔の構造図
従来のレントゲン検査では、上顎洞などの評価は可能ですが、蝶形骨洞など深い位置の副鼻腔炎の評価は苦手でした。その点CTでは詳細に評価をすることができます。
長年副鼻腔炎に悩まされている方など、ご考慮ください。
また、鼻骨骨折など外傷の評価にもCTは非常に適しています。ご相談ください。
CT 撮影例
2 補聴器相談医、補聴器適合判定医師による補聴器外来
歳を経ていくにつれて、人は徐々に老いていきます。
聞こえの神経も例外ではありません。個人差はありますが、徐々に高音域から聴力低下が始まり、徐々に会話音域も低下していきます。
難聴は認知症の最大のリスク要因と言われており、聞こえの低下を指摘されたら、早めに耳鼻咽喉科を受診しましょう。加齢による聴力低下を元に戻すようなお薬は現時点ではなく、補聴器は現時点で最も有効な対処法と考えられています。
補聴器相談医かつ補聴器適合判定医師である院長が認定補聴器技能者である補聴器会社様と協力して行います。
補聴器外来の流れ
① 一般外来
まずは当院の外来を受診し、補聴器外来希望とお伝えください。
↓↓
② 精密検査
標準純音聴力検査、言葉の聞き取りの検査など
上記を実施し、補聴器外来の日程を予約し、いったん帰宅していただきます。
↓↓
③ 補聴器外来(初回から数か月)
患者さん個別の聴力にあった調整(フィッティング)を行った補聴器を貸し出します。2週間に1回ほど来院していただき、音場(広い検査室でスピーカーでします)での聴力検査を行って、さらにフィッティングをしていきます。
↓↓
④ 補聴器外来(数か月後)
数か月の貸し出し後の聞こえの状態をお聞きし、購入希望があれば購入となります。希望がなければ、返却して終了となします。
↓↓
⑤ 互補聴器外来(購入後1か月)
初期不良など不具合がないか、やフィッティングをさらに進めていきます。
↓↓
⑥ 六聴器外来(購入後、数か月)
補聴器のメンテナンスを3-6か月に1回行います。
半年に1回程度、聴力検査を実施し、聴力の変化があれば補聴器の調整を行い、補聴器適合検査を行います。
3 DXやキャッシュレス決済を推進し、患者中心の医療を推進します
〇電子カルテと連携したオンライン順番待ち予約システム、オンライン問診システム、オンライン決済システムを導入しています。待ち時間の短縮にもつながりますので、オンラインでの順番待ち予約、問診にご協力ください。
もちろん窓口での受付でも可能です。
〇会計時にはセミセルフレジを準備しております。
Paypayをはじめとした、日ごろお使いのキャッシュレス決済に対応しております。
もちろん現金決済も可能でございます。
〇オンライン診療
便利なオンライン診療も実施する予定です。
CPAPのオンラインでの管理やお仕事終わりの夜間や休日などの時間帯を考えておりますが、詳細はまた発表します。
4 睡眠時無呼吸症候群外来と舌下免疫療法外来
睡眠時無呼吸症候群外来
ご家族の方でイビキがひどい方はいらっしゃいませんでしょうか。
いびきの中でも、無呼吸や低呼吸を伴う睡眠時無呼吸症候群だと危険な場合があります。
無呼吸まで来していると低酸素が心臓や脳の負担になり、高血圧や認知機能、日中の眠気に影響するといわれております。
また、小児ではアデノイド増殖症や扁桃肥大が原因のいびき・無呼吸もよくみられ、その場合は成長発達に影響を与えることもあります。
まずは外来でご相談ください。
鼻咽腔ファイバーを行い、空気の通り道が狭くないかをチェックします。
また、外部企業と協力し無呼吸の検査をすることができます。客観的に1時間あたり、何回呼吸が止まったり、浅くなったりしているか、身体の中の酸素の濃度も調べることが可能です。
1時間あたり40回以上無呼吸低呼吸があるような重症な睡眠時無呼吸症候群の場合はCPAP療法といって、圧をかけて呼吸を補助する医療器械を導入することもあります。
舌下免疫療法外来
毎年、スギ花粉症やダニのアレルギーのつらい症状で悩む人は非常に多いと思います。くしゃみと鼻水がひどく、集中できない、市販薬を買ってもなかなか症状を抑えることができないぐらいひどい、そういう方にお勧めなのが舌下免疫療法です。
我が国ではスギ花粉症とダニアレルギーに限り、舌下免疫療法が保険適応となっております。
舌下免疫療法の流れ
5歳以上で険適応で実施することができます。
① アレルギー検査
何のアレルギーをお持ちなのか調べる必要があります。血液検査またはドロップスクリーン検査にて検査を実施、スギまたはダニでclass 2以上のアレルギー反応がでると、舌下免疫療法をすることができます。
② 舌下免疫療法初回
はじめは院内でお薬を内服し、副作用がでないかチェックする必要があります。舌下に溶けるタブレットを置き吸収させ、1分後に唾を飲み込みます。5分は飲食を控えてください。15分ほど、強いアレルギー症状が出ないか経過観察させていただきます。
③ 舌下免疫療法 2回目
初回のあとは、2週間自宅で内服していただき、強い副作用がでていないか教えていただきます。1W後に薬のアレルギー抗原量が増えますので、注意して観察してください。
もし副作用が強い場合、舌下が強く腫れてしまったり、息苦しさがでたりする、蕁麻疹がでる、などの場合は、続けることができない場合もあります。
副作用がそれほどない場合は、継続することができます。
④ 舌下免疫療法3回目以降
月に1回、副作用がでていないか診察させていただきます。きちんと毎日を飲まないと効果が出ない薬なので、小児は親がきちんと管理をしてください。
舌下免疫療法の治療期間は3年から5年が推奨されており、長丁場の治療ですが、アレルギーを根治することができる治療ですので、おすすめです。
治療効果は80%の人にあると言われております。
院長もミティキュアを内服中で数年になりますが、目のかゆみ、鼻のかゆみが夏場でも出なくなっており、私個人は効果を実施しております。
5 めまい外来・耳鳴外来
めまい外来
めまいの原因は多岐にわたります。
めまいの一番危険なものは中枢性めまいといって、脳梗塞や脳出血に関連しためまいです。これらは、めまい以外にも麻痺や構音障害、小脳障害といった随伴症状がともう泣こうとがほとんどです。こういう場合はすぐに救急病院を受診してください。
耳鼻咽喉科では主に末梢性めまいを診察します。
めまいの中で一番多いのは良性発作性頭位めまい症という病気です。三半規管の根元に耳石器とよばれる器官があります。そこには耳石とよばれる非常に小さな小石のようなものがたくさんあり、頭の傾きや加速度を計っている器官なのですが、それが剥がれ落ちて、三半規管に迷入し、バランス感覚を乱してしまうことからおこるとされています。
原因の半規管が分かれば耳石置換を行いますが、わかりにくい場合は内服加療やめまいの注射療法を行います。
次にメニエール病については、数か月や年単位でめまいと耳閉感、難聴を繰り返し、徐々に聴力が低下していくという特徴を持っています。
こちらは内服治療や中耳加圧療法、ひどい場合は点滴治療を行うこともあります。
他にも前庭神経炎など、種々の疾患を眼振検査や聴力検査をしながら、診断していきます。
耳鳴外来
耳鳴の原因は主に聞こえの神経のダメージ、内耳障害や感音性難聴が背景にあることがほとんどです。耳鳴が気になって眠れない、高齢者が患者として多いのは難聴が多い世代だからというのが最も考えられます。
耳鳴の治療としては内服治療やカウンセリング、音響療法という様々な治療方法があります。耳鳴でお悩みの方はぜひご相談ください。
6 発熱外来
急なお子さんの発熱などお辛いですよね。
大人でも仕事をしていて、急に発熱することもあります。
インフルエンザウイルやコロナウイルスに代表されるウイルス疾患や溶連菌感染症、小児でよく流行するRSウイルスやアデノウイルス、ヘルパンギーナなど様々な疾患が考えられます。
感染対策を完備したお部屋または自家用車にて、発熱外来を実施しております。
お気軽にご相談ください。